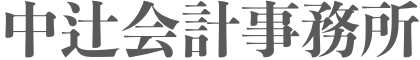今回は皆様が理解しにくい勘定科目の一つである「預り金」について見ていきたいと思います。
この「預り金」は給与を支払われた場合、必ずといって言いほどでてきます。それは従業員の方に給料を支払うときに源泉徴収を行う必要があるからです。そしてこの源泉徴収で預ったお金を従業員に代わって会社が税務署に納めます。給料をもらうたびに、毎月本人が納税するといった仕組みでは、わずらわしいですので、そういった意味でも源泉徴収は便利な仕組みです。
少し話がそれましたが、簿記ではこの源泉徴収で従業員から預かったお金を「預り金」(負債の勘定)という勘定科目で処理します。
では、給与が20万円でその源泉徴収額を4,670円として、給与を支払った場合の仕訳を見てみます。それが①の仕訳です。この場合、2つの仕訳で1つの意味を成すのです。
おそらく、難しいと思われる方がいらっしゃると思われます。その場合、②のように1つ1つにして考えてください。①と②は全く同じものです。
まず、給与を20万円支払い、その後に源泉徴収として4,670円預ったとするのです。当然、現金を預るのですから現金は増え、借方にきます。
そして、その預った源泉を納付すると③の仕訳となり預り金はなくなります。
ただ、給与を支払う人が多い場合や、源泉徴収の他に社会保険の預りなどある場合は、預り金の額が多くなり決算のときに残高が合わないといったことがよく起こりますのでので、くれぐれも預り金の残高にはご注意してください。
① (借方)給与 200,000 (貸方)現金195,330
(貸方)預り金4,670
② (借方)給与 200,000 (貸方)現金200,000
(借方)現金 4,670 (貸方)預り金4,670
③ (借方)預り金 4,670 (貸方)現金4,670